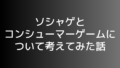この記事をPCからご覧になっている人は、既にWin11へのアップデートを済ませていますか?
Microsoftよりアメリカ時間の「2025 年 10 月 14 日」をもって、サポートを終了する旨のアナウンスされています。
アナウンス自体は、ずいぶん前に流れていたため、忘れてる人もいるのではないのでしょうか?
普段使用しているノートPCのCPUが初代i7なので、Win10のサポート終了後の身の振り方を考えなければいけなくなりました。
今回は、Win11へのアップデートまでの話とその後に悪戦苦闘した話をしていきます。
Windows10からどんな選択肢が考えられるのか?

Win10のサポート終了を見据えた身の振り方を考えていきます。
Windows10のサポート終了を見据えた選択肢を考える
正確なサポート終了時期を把握していなかった昨年末に、ふと頭の中に「Win10」のサポート終了後のことが浮かんできました。
考えた末の選択肢は下記の3つでした。
- 部屋に転がっているPCパーツを使用し、Win11が使えるPCを組む
- 当時使用中のノートパソコンにLinux系OSをぶち込む
- 危険を承知でWin10を使用し続ける
1番目の選択肢は追加のディスプレイを購入しなければならないだけでなく、部屋のレイアウト的にも邪魔にしかならないため論外でした。
3番目の選択肢もネットサーフィンを主として使用しているため論外です。
よって、2番目の選択肢であるLinux系OSをぶち込むのが、一番であるという結論に至りました。
予想もしていなかった問題にぶち当たる
色々考えた末、Linux系OSをぶち込むことにし、LinuxのOSについて調べることにしました。
LinuxのOSは基本的にオープンソースであり、無料で豊富な種類の中から選んで使えることが最大の利点です。
※因みに、現在WindowsはOS単体では安いHomeでも2万円前後しています。
Linuxに乗り換えるうえで、「Windows」のような操作感であること条件としており、そのようなOSがあることも把握していました。
しかし、調べていくうちにとんでもない事実が判明してしました。
それは、「Cent OSのサポートが終了していた」と「Red Hat社による公開リポジトリ停止」です。
今まで、しっかり調べていなかったのが悪いのですが、使用を検討していたOSが使えなくなっていました。
なら同じ系統の別OSを使えばいいじゃんと思うかもしれませんが、現状調べた感じでは殆どのOSが公開リポジトリに紐づいており、いつまで使えるのかなど不透明になっています。
そのため、今後のことも考えるとLinux系のOSを使わない方が良いという考えに至りました。
「Linuxに慣れている人であれば問題ないんだろうな。」と考えると少し勉強しなきゃなと考えてしまいますが、如何せん入口が分からない(笑)。
思わぬところから現れた救世主
色々考えた末にたどり着いた「Linux」にも頼れなくなり、絶望しているところに朗報がありました。
それは、買うだけ買って使われていなかったノートPCが眠っているということです。
「もうこれしかない!」となった私は、そのノートPCに全てをかけることにしました。
まずは、Win11に対応しているCPUであるかを調べてみることに…。
な、なんと!対応しています!
しかも、ギリギリのCore i 第8世代!
本当に危なかったぁ。
ということで、結局Win11へのアップデートを選択することになりました。
ノートPCのスペックを紹介!

救世主として現れたノートPCのスペックを紹介していきます。
ノートPCのスペックアップ!驚きの事実も⁉
Win11へアップデートするにあたり、事前にPCのスペックを調べてみたら、下記の通りでした。
| CPU | intel Core i-8130U |
| メモリ | 8GB |
| ディスク | 512GB (SSD) |
| グラフィック | インテル内臓グラフィック |
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| スピーカー | ONKYO |
| カメラ&マイク | 有 |
とりあえず、筆者が気になるスペックのみを表記しました。
とりあえず、ディスクを交換しようと思いPCを分解してみたのですが、早速問題が発生。
なんと、SSDはSSDだったのですが、「M.2」と呼ばれるSATAのSSDであり、筆者が使用しているものが使用できないことが判明しました。
しかも、普通のSSDを収納できる分だけのスペースがあるにも関わらず、何故かわざわざ変換をかまして「M.2」にされているのです。
これには、ショックを受けてしまいましたが、とりあえず元に戻し、Win11への「クリーンアップデート」を実行しました。
メモリの容量を増やしたい!
Win11へのアップデート後、特に問題なくPCを使用していました。
ですが、どうしてもメモリの容量を増やしたくなるのは、PC好きの性ですかね。
そもそも、Win11でメモリが「8GB」しかないのは少し心許ないです。
できれば、「16GB」くらいは欲しいところですかね。
ということで、PCのメモリ部分を開き確認したところ、なんと2枚挿しで「8GB (1枚で4GB)」でした。
ですので、手持ちの「8GB」のメモリと交換し、現在は「12GB」という中途半端な容量で使用しています(泣)。

動作が重くなった!衝撃の事実も⁉

Win11へ移行後に絶望した話をしていきます。
動作が重くなった!
普段は、ネットサーフィンをしたり、YouTubeやTwitchを観たりしているくらいです。
そのため、少しくらい動作が遅くなっても気にはしていません。
ですが、いつからか再生中の動画がカクついたり、全画面と通常画面の遷移時に画面がフリーズし、音声だけ流れる現象が発生するようになりました。
セキュリティソフトでフルスキャンしても何も検出されません。
試しに、タスクマネージャーを開き前述した動作を繰り返してみると、CPUの使用率が100%で張り付いていることが判明しました。
また、併せてメモリも90%近く使用されていることも分かりました。
衝撃の事実が判明
最近のメーカー製のノートPCはコストカットのため、CPUがはんだ付けされていることが多いです。
まあ、そもそも分解することは推奨されていませんし、交換を前提で買う人も少ないからなのでしょうが、こういう時に交換できればと考えてしまいますよね。
ですので、メモリの増設もしている今、最後の足搔きでCPUをブーストするしかないと考えました。
CPUをブーストするべく、PCを再起動しBIOSの設定画面で、CPUの設定項目を確認してみました。
すると、なんと!既にブースト済みだったのです。
マジで絶望しました。
放置していたPCなので、購入後にブーストしたとは考えられません。
ですので、わざわざ「U」の付く低消費電力CPUを使用しているのに、何故か工場出荷時に既にブースト済みだったと考えられます。
変換をかましてまで「M.2」だったことと言い、CPUが既にブースト済みだったことと言い、悪意を感じてしまいます。
原因を探る
結論から言いますと、ブラウザの拡張機能が原因でした。
CPU使用率が100%で張り付いてしまっている原因を探ることにします。
タスクマネージャーで確認する限りでは、普段使っているブラウザでの使用率が高いことが分かりました。
しかし、これまでと同じくYouTubeやTwitchを観ているだけなので、CPUの使用率の大半を占めているのが、いまいち理解できません。
ですので、とりあえず要らないアプリや機能を削除したり、停止したりしてみましたが、一向に改善しませんでした。
もやもやして過ごしているある日、とある配信者の配信を流しているときに、何故か突如炎上し、コメントがものすごい速度で流れていました。
その時に原因が判明します。
コメントは物凄いスピードで流れているのに、映像が止まったままになっていたのです。
よくYouTubeで切り抜き動画を見ている人は、右から左へとコメントが流れている動画を目にしたことがあると思います。
あれは元々、ニコニコ動画で使用されている機能であり、YouTubeやTwitchに標準搭載されている機能ではありません。
そのため、コメントを流す機能を使用するにはブラウザの拡張機能を使用するしかありません。
その結果、CPUに負荷が掛かり100%に張り付く事態になっていたのでした。
コメントを流すブラウザの拡張機能を停止させることで、CPUの使用率が落ち着き、安定して使用できています。
まとめ
Windows10のサポート終了まで残り1年を切り、どうしようか悩んでいる人もいるのではないかと思い、今回の記事を書かせていただきました。
また、Windows11へアップデート後の苦悩についても書いてみましたが、愚痴のような感じになってしまっていますね(笑)。
メーカー製PCの闇を垣間見ることができる出来事でした。
まあ、つまり何が言いたいのかというと、下記の4点になります。
今回の記事は以上となります。
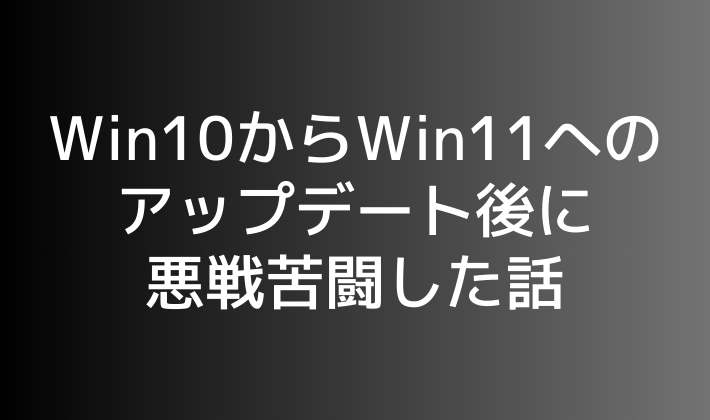
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4137555f.654c3d7d.41375560.7cb44b0e/?me_id=1213310&item_id=20523548&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5373%2F0889842905373.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)